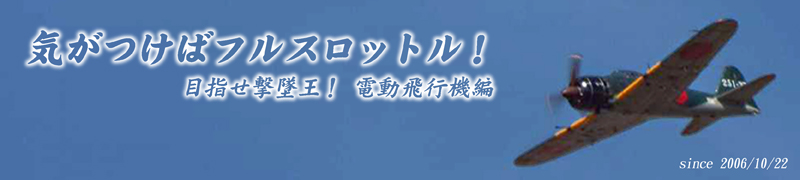
| FMS改 三菱 零式艦上戦闘機五二型 21214號 作製記 壱 |
|
|
|
|
| 2021/12/01 作製作業からこの記事編集まで時間が経ってますので当時を思い出しながらまとめています。 あまり参考になる事もありませんが私自身への備忘録として残しておきます。 実際には何度か作り直したり、細かい試作を繰り返した事もありましたがそれらはカットし大筋だけにしてあります。 また、色々な作業を同時並行で進めていたので各項目によって時系列が前後している個所があります。 |
|
|
|
|
| 思いつき 2020/12/01 | |
| 数年前に流行った電動モデルでのエンジンサウンドシステムの搭載や機銃の発光ギミック・・・今や機を逸した状態かも知れないけどやってみたく零戦五二型1,100mmで一部を試したものの無理だった。 大きいサイズの機体ならもう少し色々とできるのでは? エンジンサウンドや機銃の発光が搭載できるのでは! と長らく心に浮かんでは消えていました。 大きいのだとFMS製零戦で1,400mmがある!でも・・・あれは二二型だしいまいちテンションが上がらない・・・。 そんなある日、ネットを徘徊していたらYoutubeで零戦二二型から五二型に改造した機体を発見! そだね、キットを元にして作ればいいんだね♪と心躍らせお取り寄せしたのが始まりです。 |
|
|
|
|
| キット紹介 2020/12/10 | |
| FMS 零戦二二型 1,400mm スケールサイズは約1/8.5 9年ぶり2度目の購入! 以前零戦二二型作製の際にキットは見ておりますが今回もサラっと見ていきます。 |
|
| 9年経つうちにモーターやESC等なにかとアップデートされているようです。 | |
| 以前と同様、整然としております。 塗装の色味と質がかなり変わったように感じ少し陸軍機っぽい色になっています。 |
|
| 主翼上面 1,100mmと1,400mmではかなり見た目から来る圧が違いますね。 いやぁ、大きい大きい♪ 相変わらず警告の赤いラインが太い。 |
|
| 主翼下面 エルロンとフラップのサーボおよび引込脚がセットされております。 以前は主脚内側カバーにわざわざ開閉用のサーボがありましたが今は簡易なピアノ線。 |
|
| 胴体 大きいだけで工作の夢が広がります。 見ている分には色々と積めそう! |
|
| 機首 モーター取付済みです。 エンジンカウルの印象は変わらないなぁ。 何となく重厚。 |
|
| 操縦席 搭乗員はFMSでは毎度おなじみの人。 余って仕方ない。 |
|
| 胴体後部 尾輪は変わらず引き込まず・・・。 |
|
| 胴体内部 ESCおよびエレベーターとラダーのサーボが取付済み。 この時点では広く見えます。 |
|
| 水平尾翼・垂直尾翼の形状は以前より変更なし。 ペラ一式と爆弾が付属しております。 爆弾より燃料タンクが欲しい・・・装備する事は多分ないけど・・・。 |
|
| 機銃やフィレット等アクセサリー類に配線コネクターです。 | |
|
|
|
| 送信機アップデート 2020/12/10 | |
| Futaba T6K 送信機 今までこの企画に躊躇していたのは送信機の事情もありました。 愛用の送信機ですが6CHです。 1:エルロン 2:エレベーター 3:スロットル 4:ラダー 5:フラップ 6:ギア と基本操作に全てのチャンネルを使っており空きがありません。 今まで充実の6CHと思ってきましたが今回は機銃に一つ、カウルフラップに一つとあと2CH欲しい! もっと多チャンネルの高級品に更新しないとダメなのか・・・と思い今まで諦めておりました。 |
|
| ところがネットを徘徊しているとFutaba CIU-3と言うものを使用すればT6K送信機のファームウェアをアップデートでき、8CH仕様になるとの事を発見! これまで通りT6K送信機が使用できるとなれば余計な出費も抑えられ新送信機への在来機の設定データを移し替える必要もなくオペレーション上負荷がかかりません。 喜び勇んで購入しました。 高級プロポへの更新に比べたらとても安価です。 |
|
| 機体を購入してから送信機アップデート検証と順序が逆ですがとりあえず試してみます。 ネットからダウンロードしたファームウェアアップロードの手引書。 |
|
| アップデートすればこうなります!の説明書。 何か他にも色々追加される機能があるらしいけど、とりあえず2チャンネル増えたらそれでいい。 |
|
| 手引書通りに行い問題なくアップデートができました♪ 起動画面に一瞬Version3が表示されます。 受信機にESCやサーボを繋げてテストしたところ無事に2CH増えました。 これで憂いなく作業に入れます。 |
|
|
|
|
| 機体形状考察 2020/12/11 | |
| スケールを合わせた図面と比較し各部のサイズ感や形状を確認していきます。 | |
| 五二型への改修において一番悩ましい主翼。 | |
| 片翼で40mm短い・・・同スケールにした場合スパンは1,320mmほどか・・・。 カットした場合FLTに与えるへの影響は如何程か? 翼端をカットした方が良いのか・・・それともカットせずエルロン形状の変更だけに止めるべきか・・・悩ましい。 |
|
| 水平尾翼はサイズ通りになっております。 二二型であれ五二型であれエレベーターの形状が間違えているので手直し必要です。 この位の改修なら特に問題ありません。 |
|
| 胴体全長のサイズほぼ思ったようにきています。 | |
| 若干ディフォルメが入り間延びしてますが許容範囲内かな! どうにも気になるのは黒いスリットの位置くらいかな・・・。 |
|
| 垂直尾翼はそのまま使えそうです。 | |
|
|
|
| 作製計画2021/12/21 | |
| 大前提として零戦二二型から五二型への改修。ダミーエンジンのディティールアップ。尾輪引込への改修。 既存翼端灯の維持と尾灯の追加。エンジンサウンドの追加。機銃の発光とサウンドの追加。エンジンカウルフラップ動作の追加。・・・とりあえず現状やってみたかった事を全て盛り込んでいきます。 |
|
|
|
|
|
主翼作製 |
|
| 翼端改修 2020/12/15~23 | |
| 考察でも思いましたが・・・ 主翼の短縮を行うか! 二二型のサイズのままエルロンだけ修正しようか! 翼端をカットすればまずは翼面積減少・・・当たり前ですね。 次に形状的にカットした分の翼厚からの翼端の作り直しは上手くできるだろうか?改修するなら翼端灯の改修も合わせて考慮しなければいけない。 |
|
| おそらく主翼の長さが二二型そのままでも単機で見ればラジコンでのディフォルメと解釈しさして違和感はないと思います・・・が、今後もし二二型と並ぶ時があれば翼長が同一なのはおかしい・・・・・・やはり翼端はカットしましょう! と考察から決断まで一週間程の時間を要し手始めに翼端灯を外しました。 |
|
| 思い切って翼端をカット! これで後戻りはできません。進むのみです。 |
|
| 図面に合わせて描いたラインに沿って丸く整形しました。 | |
| エルロンをカットの際になかなかの歯ごたえを感じて見たらカーボンの芯が入っておりました。 | |
| カットした厚い状態から主に上面をカッターでスライスしながら翼端を作っていきます。 | |
| 上下の境目となる位置にラインを引きました。 | |
| 状態を見ながらカッターでスライス、その後サンディングペーパーで形状を整えました。 | |
| 少し厚ぼったくなるかも!っと思っていましたが正面から見ても良い感じになったのではないかと思います。 | |
| 翼端灯のLEDは二二型とは取り付けの位置関係が変わったので配線がクランク状になりました。 | |
| 取り付けてから念のため点灯確認! 断線等の不具合はないようです。 |
|
| エルロン先端の足りない箇所に部材を追加。 このあと形状に合わせカットし整形しております。 |
|
| 二十粍機銃 LED組み付け 2020/12/23~27 | |
| キットの機銃にそのままLEDを仕込みたいところですが・・・。 | |
| そうは都合良く配線を通せるようにはなっておりません。 | |
| 裏から見ても・・・まぁ想定されていないのだから仕方がない。 | |
| では、この長銃身に配線用の穴をまっすぐ綺麗にドリル加工できるかと言うと私には無理! | |
| ではフライングスタイロ零戦での機銃作製を応用してみよう。 | |
| 4φアルミパイプに鉛筆を突っ込んでみます。 | |
 |
収縮チューブを被せました。。 |
| 自己責任の塊作業! これを電熱コンロで炙ります。アルミパイプが入った箇所はピッタリと先端箇所はある程度硬化するまで・・・炙りすぎると先端の鉛筆にくっついて離れません。 画像は鉛筆ですが何度も形をみてやりなおし最終的に鉛筆よりやや太い金属製ボールペンで落ち着きました。 |
|
| 画像は鉛筆ですが何度も形をみてやりなおし最終的に鉛筆よりやや太い金属製ボールペンで落ち着きました。 | |
| 銃身をカットしました。 | |
| 受け部にドリルで穴を開けました。 | |
| 受け部と銃身にLEDの配線を通しました。 | |
| LEDを受け部に配置するか銃口に配置するか悩みましたが視認性重視で銃口にします。 | |
| もう片方も作製し配線コネクタを共有化しました。 | |
| 発光テスト、左右共ピカピカ点灯してます。 まずは何とか形になりそうです。 |
|
| LED配線用に溝を追加しました。 | |
| 二十粍機銃を主翼に取り付けました。 銃身は仮止めで機体完成時に角度を見ながら接着する予定です。 |
|
| フラップ改修 2020/12/27 | |
| 零戦1,100mmのフラップはプラ製となっており内部造形も再現されていたように思いますが1,400mmは発泡製で内部はディティールなしとなっております。 | |
| フラップの開閉をチェックしてみるときちんと閉まらない。 左主翼がとくにひどく中身が厚くつかえてしまいます。 右も若干気になるレベルで閉まりません。 |
|
| 左右とも内部をスライスして薄くします。 | |
| どうせ手を加えるならついでにディティールも追加します。 2mmバルサで骨組みをそれっぽく。展開時に下側は見えますが上側はほぼ見えないので骨組みは省略します。 |
|
| 主翼仕上げ 2020/12/28 | |
| 主翼は分割式ですが運用と保管の関係上、一体となった方が都合が良いため接合します。 | |
| 左右の主翼にパイプを差し込んで接着しました。 | |
| エルロンにフラップに機銃に翼端灯と配線だらけです。 | |
| 胴体と合わせ固定パーツを取り付けました。 接着剤が固定する前に左右のズレが無いようにしっかりチェック! |
|
| 左右一体になったところで再度、両翼端の整形のバランス取れているかを確認! その後、実機図面を見ながら消えてしまったモールドを再現していきます。 |
|
| 主翼下面の方がわかりやすい。まず五二型では不要となる元にあった二二型のモールドを消します。 適当にカットした1mmバルサを接着、その後木工補修パテを塗布し乾燥したところで研磨しました。 |
|
| 次に追加となる五二型のモールド個所です。 最初にカッターで薄く三角に切り取り、その後丸めたサンドペーパーで徐々に元のモールドと同じくらい広く深くしていきました。 |
|
| モールドが仕上がったらサーフェイサーを吹き付け研磨しながらモールドの状態を確認。 削った個所の発泡の目も消します |
|
| 上面も同じように修正していきます。 | |
 |
加工後の様子、下面に比べて修正は少ないです。 |
| 二二型と五二型では細かいところでモールドの違いがありますが全てにこだわっているとキリがありません。 ただ、二十粍機銃取り付け部のバルジと排莢口は気になるポイントなので追加加工しました。 |
|
| サーボの配線を溝に沿わし目隠しのテープを貼りました。 すでに主脚とフラップ内部に塗装をしてあります。 |
|
| 翼端灯のクリアパーツはサイズに合わせてカットし元の位置に接着。 この当時、通常はクリア状態から発光したら緑や赤になるものはないのであらかじめ各々にクリアーレッドとグリーンを塗装しました。 |
|
| レンズカバーをそのまま利用しようかと思いましたが少し厚ぼったいような・・・。 | |
| 主翼の作業はこれで完了です。 | |
|
|
|
| 胴体後部作製 | |
| 尾輪引込み装置追加 2020/12/29~30 | |
| FMSの1,400mm以上のクラスP51やF4Uは尾輪引き込み仕様になっておりますが残念ながら零戦は固定式です。 以前、零戦五二型1,100mmや雷電でやっている作業ですので少し拡大すれば同じことが可能かと! |
|
| 零戦1,100mmの時と同様ネジを外しても全く外れる気配がありません。 尾輪ユニットは交換用パーツとして販売されていますが簡単に交換はできないようです。 |
|
| 尾輪と合わせて尾灯も取り付けの加工をするため尾部を切り取りました | |
| 尾輪ユニットと尾部を分割しました。 | |
| 尾輪ユニットは零戦1,100mmと同じ構造です。 | |
| まずは尾輪ユニットを全ばらし。 | |
| いつもの画材用のヒンジを尾輪ユニット本体に接着しました。 | |
| 車軸をユニットに合わせ余分な軸をカットしました。 | |
| ホーン取り付け個所を六角形に整形しました。 | |
| ホーンを軸にネジ止めしました。 | |
| 相変わらずネジでギュ~っと締めこんであり回転しません。 | |
| ネジをシャフトに変更し飛び出ないようにしました。 またホイールとステーの干渉する箇所を削りました。 |
|
| 1mmカーボンで引込みケースを作製していきます。 | |
| 形状は零戦1,100mmや雷電と同様でひと周り大きいです。 | |
| ケースに尾輪をネジ止めしました。 | |
| 開閉用のカム、アルミパイプは3φです。 | |
| 引込みユニット完成。 以前の画像の使いまわしのようになっています。 |
|
| 胴体後部に硬化まで24時間の耐衝撃軟性エポキシで接着プラス中央部をネジ止めしてます。 | |
| 尾灯追加・尾翼組み付け 2020/12/31~2021/01/01 | |
| 今回、翼端灯はそのまま残しておりますが。主翼上面にある2つの編隊灯は小さくとても発光仕様にする事は無理です。 翼端灯があるならせめて尾灯は追加しようと思うので組み込んでみます。 |
|
| 尾灯を仕込む箇所をカットしました。 左右に分割しました。 |
|
| LEDは脚の長い方が+(アソード)で短い方が-(カソード)だそうです。 逆接すると即破損します。何本かお釈迦にしました。 もうひとつ制限抵抗なるものが必要との事・・・案外難しい。 使用するLEDのVF値と電流と電圧で決まった抵抗値を使用しなければならず当時は調べまくって結局無線パーツ屋の店員に聞いて購入しました。 記憶ではLEDは3Vで抵抗は150Ωだったと思います。 |
|
| 尾部内側に溝を掘ってLED配線を這わせます。 画像は仮に合わせていた時で制限抵抗がついていません。 |
|
 |
尾部両面を合わせて接着しました。 尾灯はこれで一生もの、球切れしても交換はしないつもりです。 尾灯のクリアーカバーは後に接着します。 |
| 以前、零戦二二型を所有した際に二二型だからスルーできたエレベーターの形状の違い。 今回は五二型なので手直しをしました。 |
|
| 翼端をカットしそのままエレベーターに接着しました。 | |
| 主翼と同じように翼端とエレベーターを整えていきます。 | |
| 尾灯の配線を胴体内に通していきます。 都合よく胴体内に空間がありました。 |
|
| 水平尾翼を胴体に接着しました。 | |
| 続けて垂直尾翼を接着固定しました。 | |
 |
尾部を接着しました。 |
|
|
|